![]() どんな症状に?(適応疾患)
どんな症状に?(適応疾患)
![]() どうして効くの?
どうして効くの?
![]() 心の病や不調にも
心の病や不調にも
![]() 美容にも高い効果
美容にも高い効果
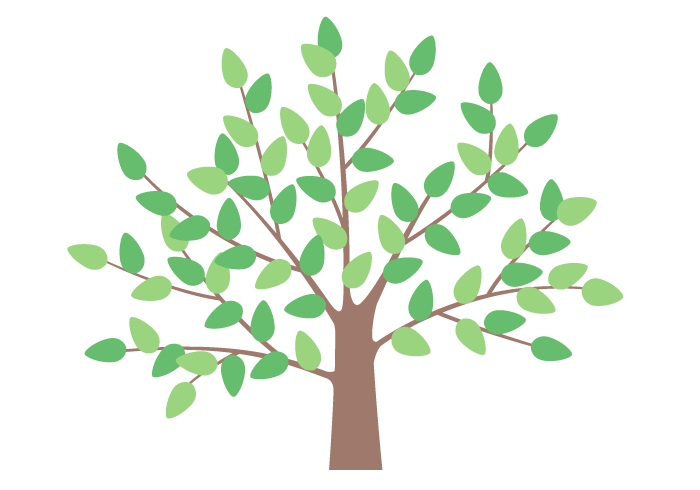 どんな症状に?(適応疾患)
どんな症状に?(適応疾患)
東洋医学では現代の医学とは異なった視点から体や心を診ていますので、病名に関わらずさまざまな不調や症状にアプローチすることができます。
またWHO(世界保健機関)によっても、多くの鍼灸適応症が発表されています。
当鍼灸院では、婦人科疾患をはじめ下記のような不調や症状に対応しております。
※詳細は疾患名をクリック/タップ
また病名のつかない不調や病院に行ってもなかなかよくならない症状、何となく調子が悪い場合などにも鍼灸は適しています。
健康増進や心や体のメンテナンスとして、定期的に受けて頂くのもおすすめです。
ただしひどい発熱や急に現れた強い症状、大きなケガなどは、病院で処置を受けて落ち着いてからお越しください。
「こんな症状に鍼灸はどうかな?」と思われたら、どうぞお気軽にご相談ください。
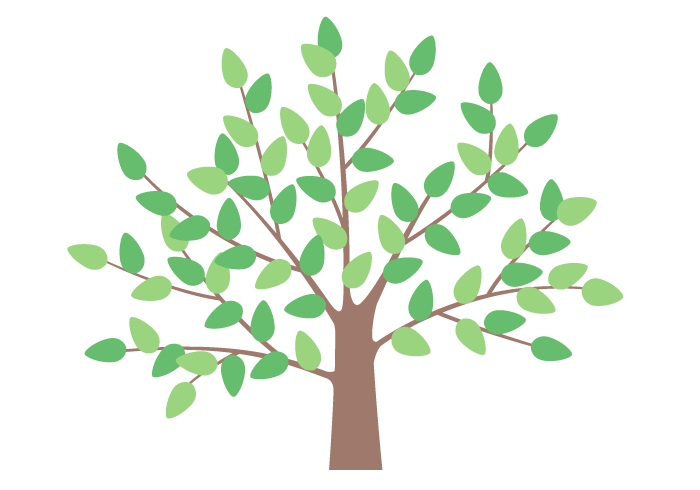 どうして効くの?
どうして効くの?
鍼やお灸は数千年前の中国で発祥し、日本には遣隋使や遣唐使と一緒に伝わってきたのではないかといわれています。
その後日本で独自に発展し、明治頃までは医療として人々を支えてきました。
どうして鍼やお灸をすることで、症状がよくなったり健康になったりするのか不思議に思われるかもしれません。
今ではさまざまな研究によって、血流がよくなったり、免疫が活性化されたり、ホルモンバランスや自律神経の働きをととのえる力があることが分かってきています。
東洋医学としては、体中をめぐっている経絡(けいらく)と呼ばれる流れやツボ(経穴)といった特別に効果を持つ場所に鍼やお灸で刺激を与えることで、その人の持つ治癒力が高まり症状や病がよくなっていくと考えています。
まだ解明されていない部分が多い東洋医学ですが、長い歴史とともに先人たちの知恵が詰まった医療として今でも多くの人の健康の助けとなっています。
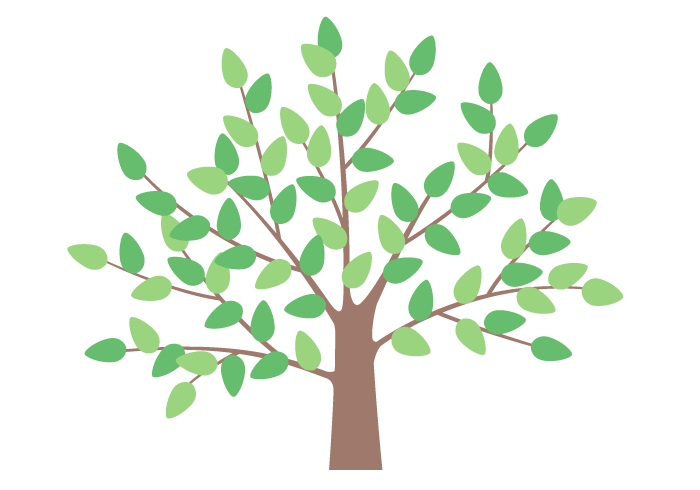 心の病や不調にも
心の病や不調にも
悩みや落ち込みから抜けられなかったり、何をやっても元気が出ない、理由も分からず不安など心の状態が不安定だと本当に辛いものです。
元気を出そう、気持ちを切り換えようと心の病や不調を心から解決しようとするのも一つの方法ですが、鍼灸で体から心にアプローチしてみませんか。
東洋医学では心と体は分けることなく一つのものだと考えています。
鍼灸で体のバランスが少しずつととのってくると、いつの間にか心もととのい楽になってきます。
無理に元気を出そう頑張ろうとしなくても自然と心が明るくなってきて、悩みが悩みでなくなったり状況を変える力が湧いてきます。
明るい方へ向かう心の力は本来自然なもので、必ず誰にでも備わっています。
鍼灸でリラックスしながら一緒に心も楽にしていきましょう。
※鍼灸と併用してカウンセリングを希望される方には、提携している臨床心理士(公認心理師)のご紹介も行っております。お気軽にご相談ください。
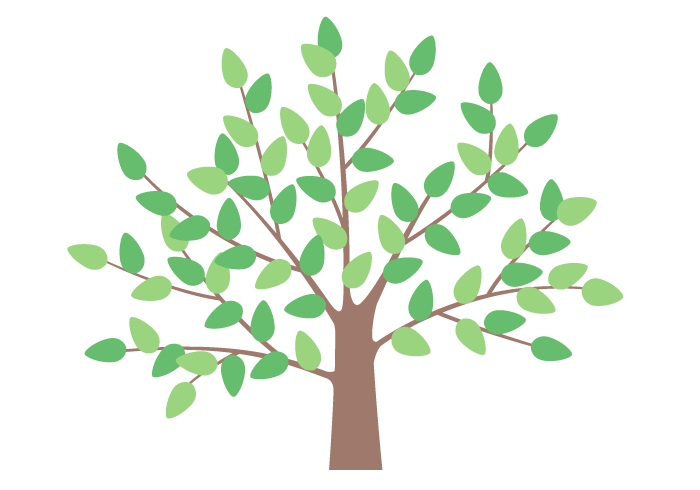 美容にも高い効果
美容にも高い効果
鍼灸で全身を施術することでホルモンバランスや自律神経の働きが整い、肌につやが出てきたりむくみやたるみが改善されていきます。
当治療室では美容を中心としたコースも設けております。
こちらは鍼やお灸で全身を施術することで内側から体のバランスを整え、お顔には「てい鍼」という刺さない鍼を使って血流をよくしてむくみやたるみなどの改善を目指します。




